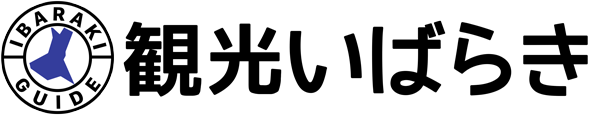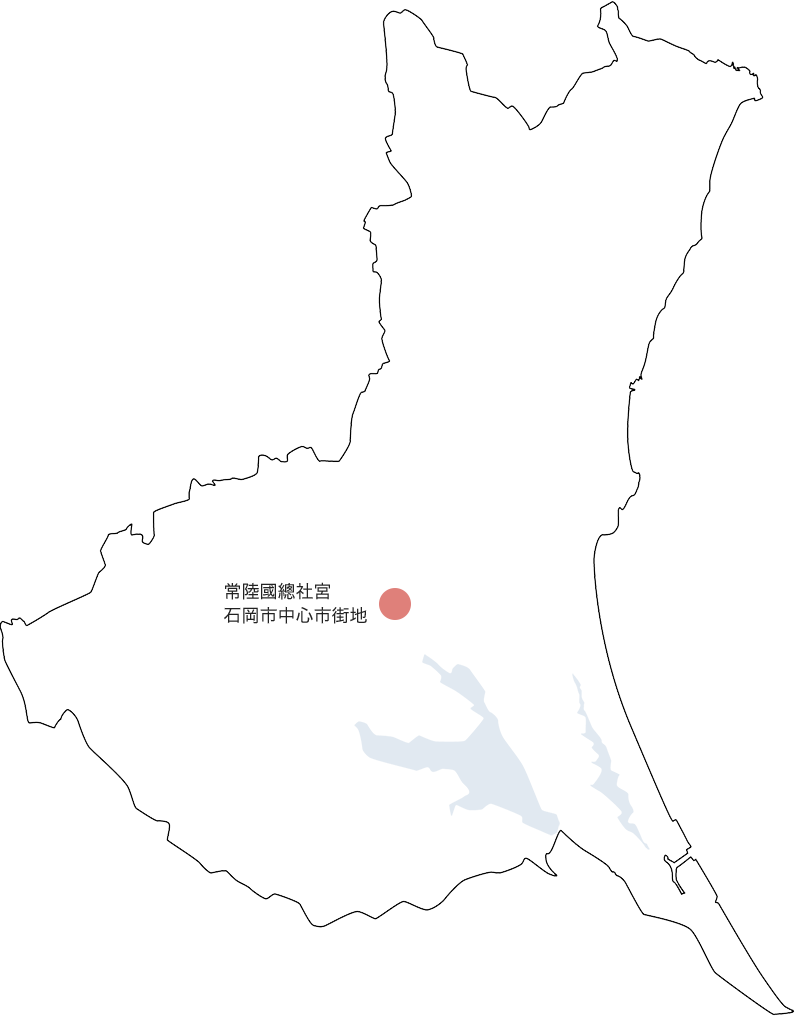3年ぶりの開催・石岡のおまつり(常陸國總社宮例大祭)
石岡市
令和4年9月15日(木)、17日(土)〜19日(月・祝)
石岡のおまつりは正式には常陸國總社宮例大祭といい、創建千年を誇る古社・常陸國總社宮の最も重要なおまつりです。
関東三大祭りのひとつにも数えられ、菊花紋を許された格式ある神輿をはじめ、絢爛豪華な山車や勇壮な幌獅子など40数台が市中心部を巡行します。例年、おまつり期間中3日間で50万人以上の見物客が訪れます。
ことし令和4年度は、新型コロナウィルス感染症対策を十分にとったうえで、3年ぶりに通常通り開催されることになりました。




迫力と熱狂の3日間
石岡のおまつりは「正月やお盆には帰省しなくても、おまつりには帰る」と言われるほど、出身者にとっては思い入れのある祭りで、石岡市民にとって1年間でもっとも熱くなる日であると、石岡市の公式サイトで紹介されるほど地元にとってなくてはならない存在のおまつりです。
石岡のおまつりは、毎年交代で15年に一度務める「年番町」を中心に行われます。年番町に当たる町は、前年のおまつり最終日に引継ぎを行い、当年のおまつり最終日に次の年番町に引き継ぐまでの1年間、町ぐるみで神社への奉仕活動を務めます。
おまつり期間中は、年番の町内に「仮殿」を設け、初日の神幸祭で常陸國総社宮から大神輿を迎え入れてから最終日の還幸祭で大神輿が還御するまで、總社宮の祭神の分身である御分霊の滞在拠点となり、その年のおまつりの中心的な役割を果たします。
神幸祭から還幸祭までの3日間は、2千人を超える供奉行列や、神様をおもてなしするためのさまざまな催しなどが行われ、敬老の日を含む3連休にあたることもあり、全国からたくさんの観光客・見物客も訪れ、夜中まで賑わいます。



石岡のおまつりのスケジュール
令和4年9月15日(木) 例祭
毎年9月15日に常陸國總社宮の本殿で行われる、例大祭で最も重要な神事です。
神社本庁の献幣使を迎え、「正服」という最も格式高い装束を身に着けて厳粛に行われます。
例祭では観光行事は行われません。
令和4年9月17日(土) 神幸祭
9月の3連休の土曜日に行われます。
常陸國總社宮の分身(御分霊)が大神輿で年番町の仮殿へ渡御する祭です。午後2時の花火を合図に、氏子町以下2千人を超える供奉行列や幌獅子ともに、大神輿が出御します。
令和4年9月18日(日) 奉祝祭
9月の3連休の日曜日に行われます。
神様への想いを競い合うかのように、さまざまな催事が行われ神様に「おもてなし」をする日です。
常陸國總社宮境内での奉納相撲や神楽殿での巫女舞、染谷の十二座神楽等が奉納されます。駅前通りでは幌獅子や山車の大行列から仮殿祭が行われ、町の熱気は最高潮に達します。
令和4年9月19日(月・祝) 還幸祭
敬老の日にあたる9月の3連休の月曜日に行われます。
二晩を過ごした年番町の仮殿を離れる神様を見送る日です。
午後2時に年番町御仮殿より大神輿が出御し、神幸祭と同じ供奉行列で常陸國總社宮へ向かいます。神事が終わり神様が本殿に戻った後、年番町の引き継ぎが行われ、夜更けまで名残を惜しみます。
常陸國總社宮
常陸国の中心である茨城県石岡市に鎮座する古社。
現在の茨城県が常陸国と呼ばれていました約1300年前の7世紀頃、現在の石岡市には常陸国の中心地である国府があり政治・文化の中心地として繁栄していました。
国府の長官(国司)の重要な任務のひとつに、国内の神社の管理と祭事の運営があり、祈りを捧げるべき神々を一同に集め、祀ったのが「總社」でした。
常陸國總社宮では一年を通じてさまざまな祭りが行われていますが、最も重要かつ盛大な祭典が例大祭、通称「石岡のおまつり」です。

Information
石岡のおまつり
会場
JR石岡駅前及び石岡市中心市街地
アクセス
お車でお越しの方
常磐自動車道 千代田石岡ICより国道6号線水戸方面へ3km
電車でお越しの方
JR常磐線 石岡駅下車 徒歩20分(約1.2km)
お問合せ
石岡市観光協会事務局(石岡市観光課内)
TEL: 0299-43-1111